新着情報
9-1. 図面 (10)
手描きで図面を描く際にはいくつかの道具を使用します。宮崎駿のアニメ「紅の豚」に飛行機の設計をする少女が登場しますが、そこで製図台が使われていました。ドラフターと呼ばれる台なのですが、過去には設計事務所といえば多くのドラフターがならんでいたものでした。
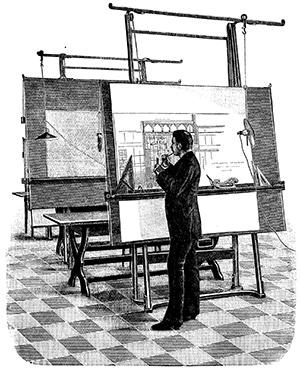
図9-1-3:ドラフター
上図は19世紀に使われていた建築家のドラフターです。基本的には平行、直角を簡単に取れるように定規が駆動する仕組みとなっています。ドラフターはそれなりに大きなものですが、より簡易なものとしてはT定規というものがあり、製図台に対してTの上辺をひっかけて平行をとり、それに三角定規を当てて直角をとるようにします。
描く道具は鉛筆、あるいはそれを下書きとしてその上にインクで清書することがありました。清書する際にも線の太さなどが図面上の重要な表現になるので、烏口という道具を使ってインキングをしていました。

図9-1-4:烏口
私たちが学生の時代にはペンにインクが入っているロットリングという製図用のペンを使っていました。

図9-1-5:ロットリング
これは製品名ではなくドイツの会社名なのですが、この製図用のペンが代表的な製品なのでそのまま通称となっています。
9-1. 図面 (9)
現在では業務上は殆どの図面はCADと呼ばれる設計用のアプリケーションを使ってコンピューター上で描かれますが、当然のことながら数十年前までは全て人の手によって紙の上に描かれていました。30代の設計者である私の個人的な経験としては、パソコン自体が高校生、あるいは大学生くらいの時に普及してきて、(インターネットを使うようになったのは大学生になってからです。)CADも大学の製図に使うようになってきた割と早い方だったように思います。ただ、私が行っていた大学の場合では、最初の課題は手描きで過去の名作住宅作品をトレース(複写)するというものでしたし、最初の自分の設計の課題も手描きが必須だったように思います。
というのも、コンピューター上では画面を拡大、縮小がマウスホイールをクルクル回転させるだけで出来てしまうので、図面の縮尺という概念が培われないという弊害があります。最終的に作られるものは、当然1分の1の実物大のものですので、それをどれだけの実感をもって図面に落とし込めるかということは、作図においてもっとも重要なファクターのひとつです。手描きで紙の上に直接描くという行為は、そういう意味でスケール感を養うのにとても重要です。実際に実務をする上でも、私の場合はCADで図面を描く前の段階で、度々手描きでスケッチをしています。
Kビル新築工事(第11回定例会議)
事業名・工事名
Kビル新築工事
日時
2014年3月19日 / 10:00~12:00
場所
トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室
出席者
- 設計監理(建築)
- トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT
- 設計監理(構造)
- K構造設計事務所
- 施工
- T社 : K(現場所長)、M(部長)、I(設備担当)、T(技術営業)
- 施工(電気)
- H社 : F
- 施工(設備)
- O社 : A
1.前回議事録の確認
- 施工 K:
- EVスイッチのLEDの件は継続で確認中です。
- 施工 K:
- 10Fの消防隊進入口が確保できていない件はいかがでしょうか。
- 設計 MR:
- 検討中です。早々にメールで回答します。
2.週間工程の説明
- 3/18にコンクリートの型枠脱型後の検査をK構造設計事務所のO氏に受けて問題はありませんでした。
3.4月月間工程の説明
- 施工 K:
- 1節の製品検査を4/1に実施いたしたい考えです、立会者はTPMからはMR氏、K構造設計事務所からはKY氏とO氏で宜しいでしょうか。
- 設計 MR:
- それでよいので予定をメールでください。
4.質疑
【1FエントランスホールのSWについて】
- 施工 K:
- 納まり図確認お願いします。
- 設計 MR:
- 立上りを設けている箇所が影として出るので納まりを再検討します。
- 施工 K:
- 分かりました。
【各階EPS出入口のSD-3について】
- 施工 K:
- 納まり図確認お願いします。セットバック部分の足元廻りの納まりはいかがでしょうか。
- 設計 MR:
- 図の通り亜鉛メッキチェッカープレート(CPL)として水抜き穴を設けてください。CPLの下にコンクリートがありますが、押出成型セメント板との間に隙間があります。板金処理を設けて2重に止水処理をする納まりでお願いします。
- 施工 K:
- 分かりました。
【2FのEPSについて】
- 施工 K:
- 平面図に設備をプロットしています、図の通りEVホール側の壁がEPS側に480mm入り込みますが設備関係はスペース的に納まりそうです、これで宜しいでしょうか。
- 設計 MR:
- これでよいです。
- 施工 K:
- また電気盤の蓋が空調冷媒配管と近いので開閉式とはせず蓋式としたいですが宜しいでしょうか。
- 設計 MR:
- よいです。
- 施工 K:
- EPS内に照明器具が配置されていませんが壁付けの蛍光灯は必要ないでしょうか。
- 設計 MR:
- 必要ですね。追加で設置お願いします。
【給湯室の設備配管について】
- 施工 K:
- 設備図を修正しましたので確認お願いします。
- 設計 MR:
- バルコニーから室内への給気口は100φに変更して天井高を2300取ってください。梁下と出入口サッシとの間に配管することになるのでサッシH=2175としてください。
- 施工 K:
- 分かりました。
【屋上の放水口のメーターについて】
- 施工 A:
- 現在設計では10Fのメーターに接続となっていますが分岐して屋上のメーターを別に設けなくてもよいでしょうか。
- 設計 MR:
- 設備設計に確認します。
【連結送水管の配管について】
- 施工 A:
- 外面ライニング仕様となっていますが、圧力配管用炭素鋼管に変更してもよろしいでしょうか。
- 設計 MR:
- 設備設計に確認します。
【汚水配管について】
- 施工 A:
- 外部露出配管の汚水竪菅をカラーVPに変更は可能でしょうか。
- 設計 MR:
- 設備設計に確認します。
【2~10Fの給水配管について】
- 施工 A:
- 架橋ポリエチレン菅先分岐工法で床転がし配管へ変更は可能でしょうか。
- 設計 MR:
- 変更で良いです。
【空調吹出しダクトについて】
- 施工 K:
- 外部階段側に外壁貫通して室内に入れる配管ルートですが、基準法または消防法上問題ないか確認する必要があるかと思います。
- 設計 MR:
- 建築指導課の設備担当者に確認します、A氏の方で消防の予防係りにも確認してください。
- 施工 A:
- 分かりました。
- 設計 MR:
- 階段部分で外壁貫通の扱いとはせず、外部階段の天井内をEPSと区画内であるという扱いでできるかも含めて検討します。
【1Fのステンレスサッシについて】
- 施工 K:
- サッシ方立が見付が細いため、たわみが出る可能性があるとのことなので検討お願いします。
- 設計 MR:
- どの程度のたわみが出るのか、一度サッシ業者さんを呼んで頂き打ち合わせをしましょう。
- 施工 K:
- 分かりました。また自動ドア開放時の戸袋部分へ巻き込み防止用の手すりか柵が図面にありませんが必要ないでしょうか。
- 設計 MR:
- ここに人が巻き込まれる危険は殆どないでしょう。必要ありません。
以上
2014.4.9 作成:MT
9-1. 図面 (8)
設備設計は給排水衛生設備や空調換気設備、消火設備などの設計を担います。給排水衛生設備とは、要するに水廻りのことで、浴室やキッチン、トイレ廻りの設備の設計で、空調換気設備はエアコンや換気扇関係の設備設計です。電気設計は電気が関連する設備を設計しますが、幹線、動力、弱電、電灯・コンセントから、通信設備(電話、インターネットなど)、火災報知器などのジャンルがそれに当たります。多くの場合、これら構造、設備、電気設計は意匠設計を元請けとして、下請け的に設計契約を結ぶことが多く、そういう意味で意匠設計が全体を統轄するので、意匠を総合設計と呼ぶこともあります。また工事の段階になると、施工者も建築、設備、電気と専門に分かれます。設計図上の意匠と構造はこの場合は建築に対応し、設備と電気はそのまま設計と施工が対応関係にあります。
形式上、このように分業がなされていますが、実際的に出来上がる建築物としては1つの大きなものです。図面上では分裂して表現されているものも、1つの全体をもった建築物として作られなくてはならないので、これらの図面をきちんと重ねあわせる作業が必要ですし、そこが元請けの施工者の実力として評価される部分です。
9-1. 図面 (7)
実施設計では基本設計で描かれた図面に対して更に詳しい内容が付加されていきます。先に挙げた図面の他、矩計図(断面図のスケールを上げたもの。断面詳細図ともいいます)、展開図、天井伏図、平面詳細図、部分詳細図、建具表などです。その他、必要に応じて建具詳細図や外構図、エレベーター図など、あるいは断熱材や耐火材の詳細を表現した図面などを作成することもあります。基本図の内容も、詳細図を検討することによって変更が加えられますので、それらを反映する作業があります。
ところで建築設計の分野においては、意匠設計および構造設計、設備設計、電気設計と、概ねこのように設計する内容に従って専門に分けることが多いです。規模が小さく比較的単純な住宅の設計などでは意匠設計が一手に構造と設備も担うことがありますが、一定規模以上の場合はこのように設計作業を分担します。意匠設計は全体のまとめ役で、関連する全ての事柄を調整します。構造設計はもちろん建物の躯体(構造体)の設計とその構造計算を行って、構造的にその建物が成立しているかを検証します。
