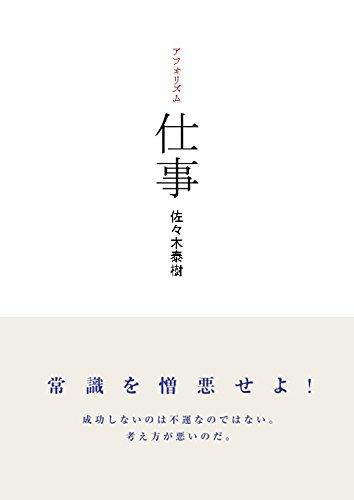新着情報
一般財団法人佐々木泰樹育英会 設立のお知らせ
当社代表取締役 佐々木泰樹が理事長を務める「一般財団法人佐々木泰樹育英会」を本日設立致しましたので、お知らせ致します。
佐々木泰樹育英会は、優れた建築専門家を目指し努力している建築専攻の大学院生や、社会正義の実現に寄与する法律家を志す司法修習生等に対する経済的支援の提供を目的としています。
本財団の事業を通じて、真の意味で豊かな社会の実現にいささかでも貢献できればと切望しております。
財団の概要、設立の趣旨などはWEBサイトをご覧ください。
当社代表 佐々木泰樹著「アフォリズム 仕事」出版のお知らせ
当社代表取締役 佐々木泰樹が著書を出版いたしました。
「アフォリズム 仕事」
「常識を憎悪せよ」「才能は例外無く意欲からのみ産まれる」など仕事に関する心に響く言葉がつまっています。
11/20(金)より、amazonで販売中です。
ぜひご覧ください。
不動産小口所有による相続・贈与対策セミナー開催のお知らせ
このたび弊社では、不動産特定共同事業法に基づく不動産運用商品「SUBLEASE-CLUB(サブリースクラブ)」を例に、
相続・贈与対策に不動産を活用する際のポイントや注意すべき点を分かりやすくお教えする
『不動産小口所有による相続・贈与対策セミナー』を開催いたします。
※お電話でのお申し込みも承っております。
フリーダイヤル:0120-627-801
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひお気軽にご参加ください。
10/11(日) 広告掲載のお知らせ
10月11日(日)の読売新聞全国版(朝刊)に、弊社「SUBLEASE-CLUB(サブリースクラブ)」の広告が掲載されます。
どうぞ、ご覧ください。
初めに選ばれる建築設計Ⅰ 建築設計業務の内容⑨
実施設計
実施設計については、本サイト実施設計・建築確認申請ページにて概要をご確認ください。
基本設計図は、設計者がオーナー様にプレゼンテーションをするためのものでした。通常、イメージパースを使用しますが、それはあくまでオーナー様にイメージを明確に伝えるための基本的な図書であることはお話したとおりです。
それに対して実施設計図は、建設会社が工事費の見積もりを作成する際に必要となるものです。収支計画に影響が大きい建築工事費は、できるだけ正確な数字を把握する必要があります。そのため実施設計図は、ビルの外装・建材から、OAフロア、内装、設備に至る詳細な指定が加わったものとなっています。
| チェックポイント | |
|